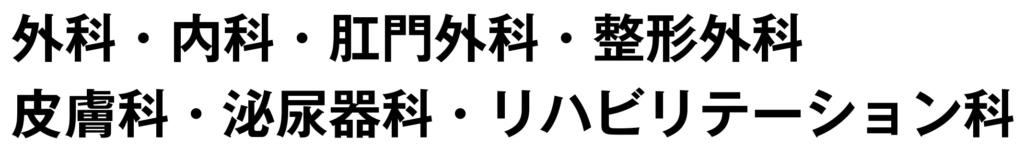漢方薬はスープだった?~医食同源のルーツと健康への秘訣~
医食同源 漢方薬はスープだった?
医者に成りたての頃、患者さんに聞かれて困ったことに「○○に良い食べ物は何ですか?」という質問があります。病気や薬の事は勉強をしていましたが、食事に関しては無頓着でした。しかし、漢方を学んだ現在では薬膳レシピを参考に患者さんの相談にお答えしています。
「医食同源」や「治未病」の言葉があるように、漢方では食事を重視します。薬は食事の延長であり、病気になってから強い薬で治療をするよりも優しい食事で病気を未然に防ぐ事が大切という思想です。この考えの元、食養で健康を維持する「食医」が医者の中で最高位とされてきました。

殷の時代の伊尹(いいん)という料理人が食医の始祖とされています。伊尹は鼎(かなえ、お鍋)で煮込んだスープ料理が得意でした。中国ではスープの事を「湯」と表現します。伊尹は美味しい湯(スープ)の他に飲むと元気のでる湯(スープ)があることを発見し、これが漢方薬の始まりとされています。

漢方薬の名前の○○湯(葛根湯、麻黄湯など)の「湯」は薬草を煮出した元気になるスープという意味です。漢方薬はスープの延長であり、まさに医食同源を表すエピソードだと思います。現在は散逸してしまっていますが、「湯液経」という伊尹のレシピ集が存在したとされます。また漢方のバイブル「傷寒論」の処方の内の大部分が伊尹のレシピを引き継いだものとも言われています。

伊尹は料理人から宰相に上り詰めたことでも有名です。鼎(お鍋)を担いで殷の湯王に近づき、料理の味で湯王の胃袋をがっちりつかみました。そして政治を得意の料理に例えて説き、宰相に抜擢されたと伝わっています。ちなみに「宰」の字は包丁をふるって料理をする意味の会意文字です。宰相とは国家を料理する人物なのです。
中国人は「食」を重視した民族であり、料理人から宰相、食医の始祖となった伊尹の逸話はこのことを良く表しています。伊尹の担いだ鼎(かなえ)は食材や薬草を料理して人々を飢えから救い、健康を養うための重要な道具でした。そして鼎はいつしか権威のシンボルにもなりました。
さて加納渡辺病院の「鼎の軽重は如何?」。伊尹には及ばなくとも、良い処方、医療を提供できるように鼎を磨き続けていきたいと思います。
書いた人
岐阜市・加納渡辺病院
外科専門医・漢方専門医 渡邊学