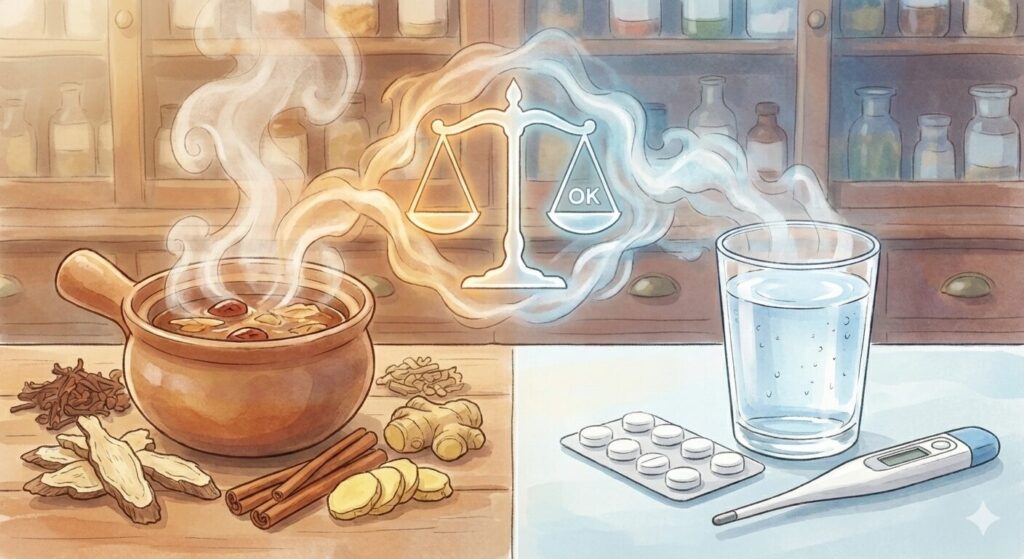かのわたコラム
現代医学は日々進歩していますが、すべての病態をよくできるわけではありません。そのため、病気になる一歩手前の「未病(みびょう)」レベルの不調には、漢方が有効な場合が多いです。
当病院では、漢方を中心に、さまざまな症状についてや医療に関する話題を掲載します。
主な配信テーマ
漢方・東洋医学
生活習慣
食事(薬膳)
鍼灸・ツボ
気になる病気・検査について
皆様の健康づくりや、日々の生活のご参考になればと思い、分かりやすく解説いたします。ぜひ定期的に当院のサイトをご覧ください。

渡辺 学 Manabu Watanabe
「一番安心できる場所」で健やかな毎日を過ごしていただけるよう、長年の臨床経験と東洋医学の知見を交えながら、皆様の心と身体に寄り添う情報を発信してまいります。
-

【風邪の疑問】葛根湯と解熱剤の併用はNG?漢方の視点でわかる正しい使い分け
葛根湯と解熱剤の併用について 風邪の漢方薬に関するよくある疑問に 「体温を上げる葛根湯と熱を下げる解熱剤を併用しても良いですか?」 という質問があります。 葛根… -


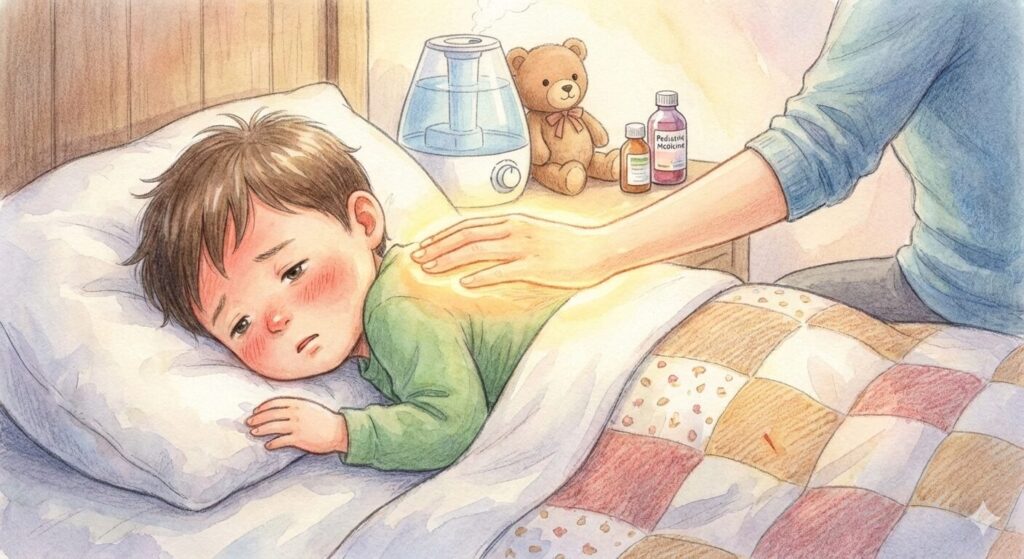
【子供の風邪対策】薬以外にできること。熱・咳・鼻水に効くツボと手当ての方法
風邪の手当て(マッサージ) 我が子がインフルエンザにかかりました。小児科を受診して薬をもらいましたが、つらそうにしているのを見るとかわいそうになります。何かで… -


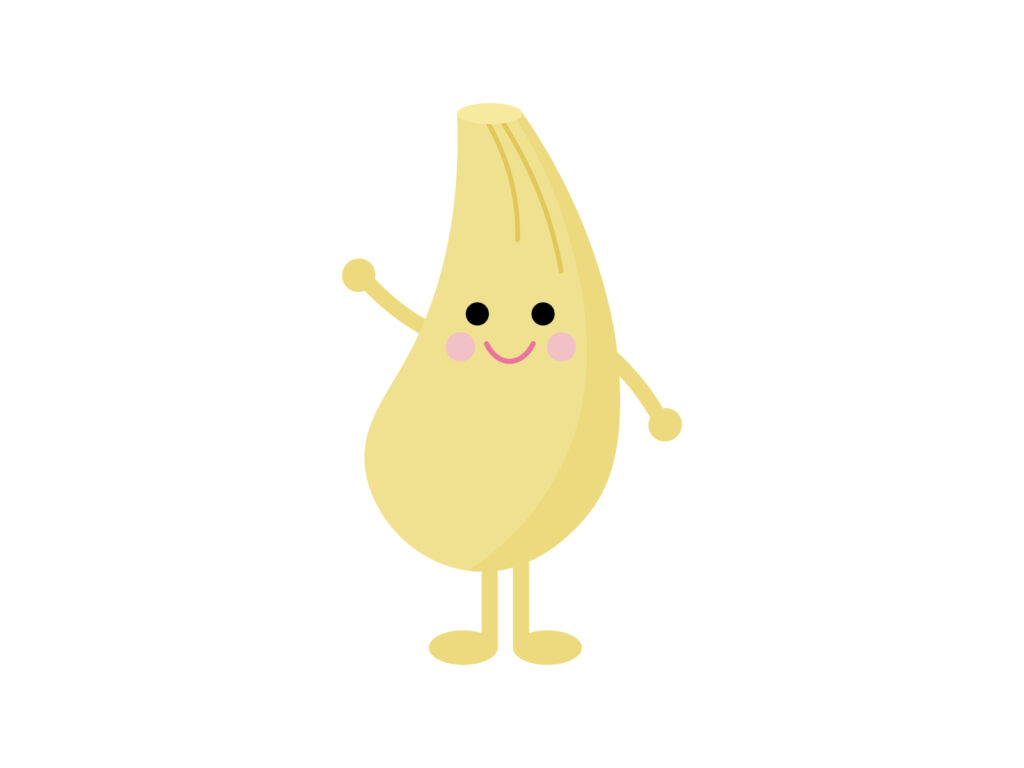
冷え性と心臓を守る食べ物「ラッキョウ」の力。胃腸も丈夫にする漢方の知恵
ラッキョウと漢方 ラッキョウは漢方では薤白(がいはく)とよばれ、心臓に効く生薬とされます。体を温めて気血を巡らし、痰を減らす効能があるとされます。胸痺と呼ばれ… -



冷え性は万病のもと!ツボを狙ったカイロの貼り方とおすすめの漢方薬
ツボを意識したカイロの貼り方と漢方薬 「冷えは万病のもと」と言います。今回のコラムでは冷え性に対するツボを意識したカイロの貼り方と漢方薬を紹介します。東洋医学… -



七草粥の驚くべき健康効果とは?「粥有十利」と食養生から紐解くお粥の魅力
七草粥と薬膳。粥有十利、お粥に10の功徳あり。 2026年も1週間が経過しました。皆さんは七草粥を召し上がられたでしょうか。みずみずしい七草粥は胃腸がきれいに… -



2026年「丙午(ひのえうま)」の意味とは?運勢や性格、迷信をポジティブに読み解く
丙午を乗りこなせ! 丙午はどんな年? 2026年の干支は丙午(ひのえうま)です。干支学では丙(ひのえ)も午(うま)も火の属性を持ち、丙午の年は火×火で炎のように陽気… -



2025年今年の漢字「熊」と漢方|万能薬「熊胆(くまのい)」から現代のウルソまで
熊と漢方 2025年の今年の漢字に「熊」が選出されました。今回のコラムでは漢方の視点から熊について記載をしてみます。 熊の胆嚢は「くまのい」と呼ばれ、高貴薬と… -



お屠蘇とブラッディーメアリー──正月の“復活の酒”で二日酔いと邪気を屠る
ブラッディーメアリーはアメリカのお屠蘇? お屠蘇は無病息災を願ってお正月に飲む薬酒であり、その語源は「邪気を屠り、生気が蘇る」事とされます。 所変わってアメリ… -



易経『天水訟』に学ぶ争いの解決法
言葉の処方箋:天水訟 易経に天水訟という訴訟、トラブルへの対処法を説いた卦があります。 「訴訟の時は真実を主張しても通らない。慎重に中道を保つのが吉。自分の要…
Popular
よく読まれているコラム
-



女性の健康を支える漢方:加味逍遙散(かみしょうようさん)の効果と活用法
女性と漢方:加味逍遙散()の使い方 漢方の勉強会で加味逍遙散()について講義をさせ… -



尿管結石の痛みを即効で和らげる漢方とツボ:救急外来の現場から
尿管結石の漢方とツボ 救急外来で若い男性が背中の痛みで悶え苦しんでいると、まず… -


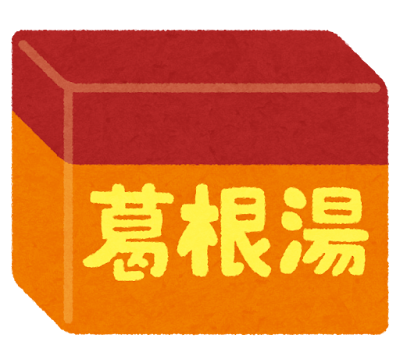
令和版 葛根湯医者:風邪、頭痛、肩こりから二日酔いまで、『葛根湯をどうぞ』
令和版 葛根湯医者 葛根湯は日本で一番有名な漢方薬の一つです。 江戸時代にも良… -



ニキビと漢方:五行から見る漢方治療
ニキビと漢方 漢方外来をしているとニキビの相談が時々あります。 今回はニキビの… -



イソップ童話:『北風と太陽』の教訓を活かした漢方治療の戦略
北風と太陽 イソップ童話に北風と太陽のお話があります。 北風と太陽が旅人のコー… -


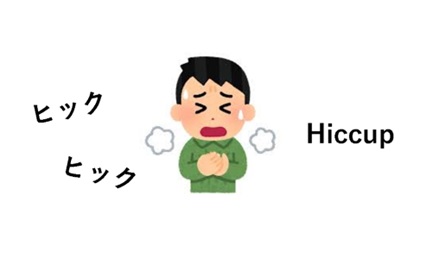
しゃっくりに悩むあなたへ。漢方や鍼灸で効果的に治療する方法とは?
しゃっくり(吃逆)の漢方とツボ しゃっくりを止めて欲しいと言う患者さんが年に数…